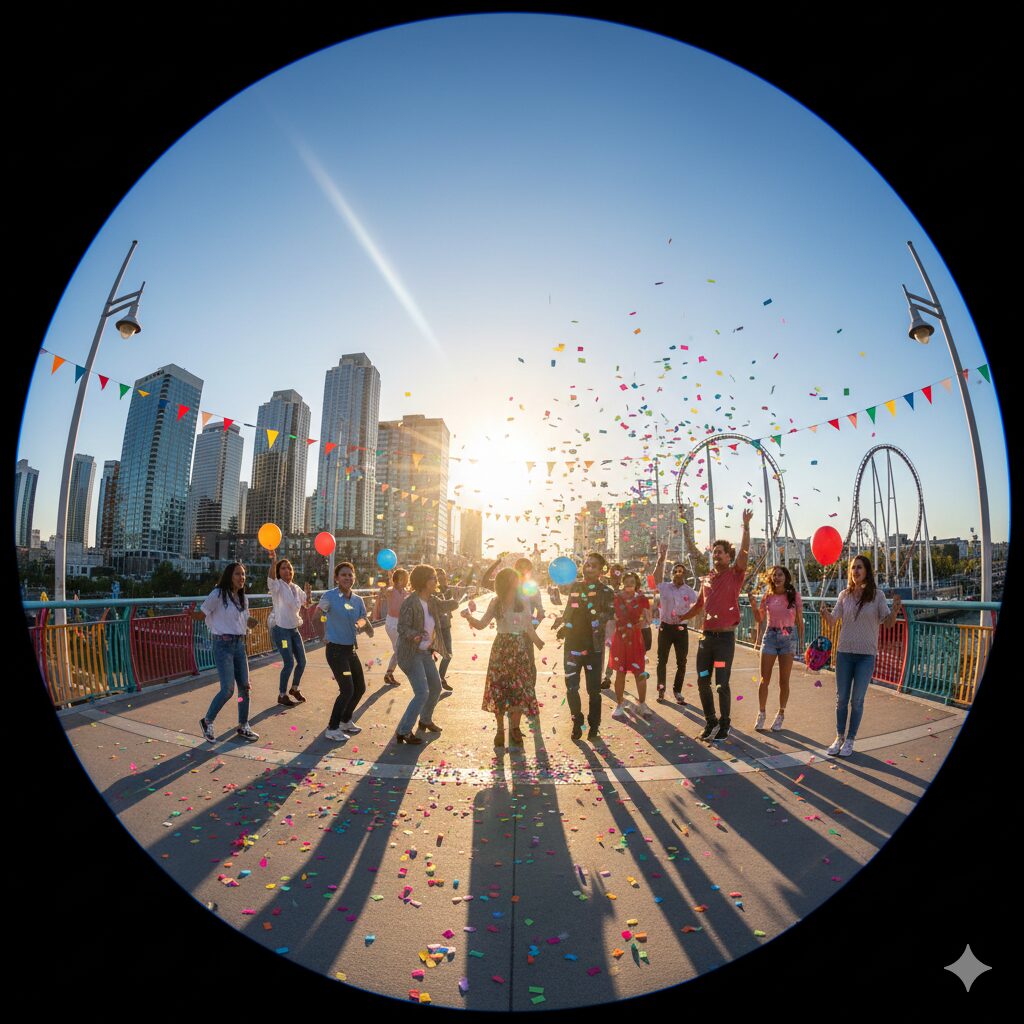RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM動画撮影での使い方
RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STMは、2026年2月にキヤノンが発表したRFマウント用の魚眼ズームです。キヤノン公式では、35mmフルサイズ対応のレンズ交換式カメラ用レンズとして「全周190°」をうたっており、7mm側で全周魚眼、14mm側で対角線魚眼まで1本で扱えることが大きな特徴です。発売予定日は2026年2月20日、国内の直販価格情報としては258,500円という報道も出ています。([Canon(Japan)][1])
このレンズは写真用途だけでなく、動画制作との相性がかなり高い設計です。公式情報でも動画撮影時の快適性を高めるドロップインフィルター対応や、2D 180°VR対応が明記されています。([Canon(Japan)][1])
つまり「ただ広い」だけの特殊レンズではなく、映像表現を積極的に作りにいくための道具として使うと価値が出ます。ここからは、実務で迷わないように、撮影前の設計、現場での運用、編集まで一気通貫でまとめます。
このレンズで動画を作る時に最初に決めること
魚眼動画が失敗しやすい最大の理由は、画角の強さに引っ張られて「何を見せる映像か」が曖昧になる点です。RF7-14mmは7mmで非常に強い湾曲と情報量を持ち、14mmでも一般的な超広角よりはるかに誇張感が残ります。したがって最初の設計は「テーマ優先」で進めるのが正解です。
例えば、街歩きなら「臨場感」、建築なら「空間の広がり」、車載なら「速度感」、人物なら「距離の近さと迫力」、商品紹介なら「中心被写体を大きく、周辺で文脈を見せる」という具合に、狙いを一文で先に決めます。これを決めるだけで、ズーム位置、被写体との距離、カメラ高、移動速度、編集テンポまで自然に決まります。
次に、7mmと14mmを別レンズ感覚で扱う設計が重要です。
7mmは「世界観を見せるモード」です。全周系の印象が強く、構図の中央に置いた主題は意外と安定して見えますが、端は大きく引っ張られます。主役を真ん中に固定し、周辺は雰囲気情報として使うと破綻しにくくなります。
14mmは「説明しやすいモード」です。歪曲は残るものの、視聴者が空間を理解しやすく、Vlogやレビューのメインにも使いやすい画角です。一本の動画で両方を混ぜるときは、7mmをアクセント、10〜14mmを本編にすると視聴体験が安定します。

動画撮影で効く、レンズ特性の実戦理解
このレンズはワイド端F2.8、テレ端F3.5です。従来のEF8-15mm F4Lより明るく、暗所でシャッタースピードを確保しやすい利点があります。([Canon(Japan)][2])
動画では、明るいレンズは単にノイズを減らすだけでなく、ISOを抑えて色の粘りを保てる点が効きます。夜景、室内、雨天、トンネル進入など、露出が瞬時に変わる環境で安定しやすくなります。
最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.35倍(14mm時)も動画で強い武器です。([Canon(Japan)][2])
魚眼は「寄れない」と誤解されがちですが、このレンズはかなり寄れます。レンズ前数センチの位置に被写体を置いても背景を広く入れられるため、料理、ガジェット、工具、メーター、手元作業などで「主役は大きいのに空間も分かる」カットが作れます。
この性質を使うと、説明動画の説得力が一気に上がります。通常の標準ズームでは背景が消え、超広角では主役が小さくなりがちな場面でも、魚眼ズームは両立しやすいです。
ドロップインフィルター対応も動画では実利が大きいです。([Canon(Japan)][1])
超広角・魚眼は前玉が大きく、前面フィルター運用が難しいことが多いですが、ドロップイン対応ならNDでシャッタースピードを守る運用がしやすくなります。昼の屋外で1/50や1/60を維持したいとき、NDを使えるかどうかで映像の質感がまったく変わります。魚眼映像は情報量が多いため、シャッターが速すぎると動きがカクついて見えやすく、適正シャッターの維持が特に重要です。

現場で使える基本セッティング
フレームレートは最初に用途で固定します。
日常Vlog、レビュー、対談、街歩きは24pまたは30p。動きの激しいアクション、手持ち追従、スポーツ系は60pが扱いやすいです。
シャッタースピードは24pなら1/50、30pなら1/60、60pなら1/125を目安にします。ここは迷わず固定し、明るさ調整はNDとISOで処理する方が映像の一貫性が出ます。
絞りはF4〜F5.6中心が運用しやすいです。魚眼は被写界深度が深く、開放でもピントは外しにくいですが、画面周辺の描写安定と露出余裕のバランスを取るとこのレンジが使いやすいです。夜や室内はF2.8〜F3.5を使い、ISO上昇を抑えます。
ホワイトバランスはオート任せでも撮れますが、カット間で色が跳ぶと編集で目立つため、屋内は色温度固定、屋外は太陽光固定を基本にすると仕上げが楽になります。
AFは顔・瞳追従を使いつつ、近接カットでは被写体優先AFに切り替えるのが安全です。魚眼は背景情報が多く、追従対象が迷いやすい場面があります。手元作業や商品レビュー時は、最初に主役へタップして追従を固定し、構図変更はゆっくり行うと歩留まりが上がります。
MFを使う場合は、超広角特性を利用してハイパーフォーカス気味に設定しておけば、歩き撮りでも破綻しにくくなります。

構図の作り方:魚眼を「効かせる」ための実務ルール
魚眼の構図は、主役を中央に置くだけで成立しやすいです。端に重要情報を置くと歪みで読み取りづらくなるため、タイトル的な被写体、人の顔、商品のロゴ、説明用テキストを画面中央寄りに集めるのが基本です。
水平線や建築の基準線を見せたい場合は、カメラの上下角を丁寧に管理します。少し煽るだけで線が大きく曲がるので、意図がないと「撮影ミス」に見えやすくなります。
動きの設計も重要です。
前進移動は魚眼と非常に相性がよく、没入感を強く出せます。横移動は周辺流れが強くなりすぎる場合があるため、速度を遅めに保ちます。
パンは小さく、チルトはさらに小さく。魚眼で大きく振ると視聴者が酔いやすくなります。躍動感を出したいときはパンで作るより、カメラ自体を前後移動させる方が見やすい映像になります。
人物撮影では、顔を中心に入れると自然、端に置くと誇張表現になります。
誇張を狙うときは、わざと近づいてパースを強めます。説明系やインタビューでは、被写体との距離を一定に保ち、14mm側を多用すると安定します。
手持ち自撮りでは、腕の長さだけで画が決まるので、7mmは背景訴求、10〜14mmは顔の自然さ重視という使い分けが有効です。

用途別プリセット運用
街歩きVlogでは、10〜14mm中心で撮ると視聴者が道順を理解しやすくなります。要所だけ7〜8mmへズームして「ここは広い」「ここは密度が高い」という空気感を見せると、一本の中に緩急が出ます。歩きながらの独り言収録は、カメラを胸より少し上に構えると背景の情報量が整います。
建築・内装紹介では、水平と鉛直の管理が最優先です。
魚眼は直線を曲げるので、全カット魚眼だと物件の印象が不正確になりやすいです。対策として、導入とアクセントを7〜9mm、本編説明を12〜14mmに分けると誇張と説明のバランスが取れます。
狭い部屋の撮影では、コーナーから対角線方向へ見せると奥行きが出ます。
車載・バイク・自転車では、7〜10mmが強力です。視界の広さで速度感を演出できます。
固定が甘いと揺れと歪みが同時に出て見づらくなるので、マウント剛性を優先し、電子補正を使いすぎない設定から試すのが安全です。補正を強めると画角が削られ、魚眼の良さが薄れます。
商品レビューでは、14mmで主役説明、7〜10mmで演出カットという二層構成が使いやすいです。
例えばキーボードなら、14mmで全体紹介、10mmでタイピング、7mmで机全景+部屋の空気感という流れにすると、視聴者が情報を取りやすいです。
最短撮影距離を活かし、被写体に寄ってから背景を見せるカットは、短尺動画でも強い印象を残せます。([Canon(Japan)][2])
2D 180°VR撮影での活用ポイント
公式情報で2D 180°VR対応が示されているため、VR用途を視野に入れた運用も可能です。([Canon(Japan)][1])
VR系は通常動画以上に「カメラ位置」が作品品質を決めます。視聴者の視点代行になるため、目線に近い高さ、自然な移動、不要な急旋回の回避が重要です。
現場では、画角の強さに頼らず、被写体配置と距離で奥行きを作ると見やすさが上がります。音の位置感と映像の方向感が一致していることも重要なので、編集前提で環境音を丁寧に収録しておくと完成度が上がります。
編集時のコツ:魚眼素材を見やすく仕上げる
魚眼素材は、撮って出しの迫力が強い反面、長時間視聴では疲れやすい傾向があります。編集では「強いカットを短く、説明カットを長く」の配分が効きます。
目安として、7mmの強い絵は2〜4秒、10〜14mmの説明絵は4〜8秒。これだけで見やすさがかなり変わります。
手ぶれ補正は後処理で強くかけすぎると不自然な伸縮が出やすいです。まず現場側で揺れを減らし、編集補正は控えめにします。
歪曲補正をかけるかどうかは、作品意図で決めます。全カット補正すると魚眼らしさが消え、部分補正だとカット差が目立つことがあります。おすすめは「説明パートのみ軽補正、演出パートは無補正」です。
色編集はコントラストを上げすぎない方が、周辺部の情報が見やすく保てます。魚眼は画面内情報が多いので、派手な色より視認性重視が仕上がりやすいです。
失敗しやすい点と対策
最初の失敗は「全部7mmで撮る」ことです。撮影者は気持ちいいのですが、視聴者は情報過多になりやすいです。対策は、1シーン内で最低1回は10〜14mmへ切り替えることです。
次の失敗は、主役を端に置き続ける構図です。魚眼の端は演出領域と割り切り、説明対象は中央管理へ寄せると安定します。
三つ目は、シャッター管理不足です。明るい日中でNDなし撮影をすると、カクついた質感になりやすいです。ドロップイン運用を前提に設計すると失敗率が下がります。([Canon(Japan)][1])
四つ目は、移動速度が速すぎることです。魚眼は速度感が増幅されるため、撮影者の体感より一段遅く動くとちょうどよく見えます。

実践テンプレート:1本の動画を組む流れ
冒頭5秒は7mmで世界観提示、次の20秒は12〜14mmで内容説明、中盤で近接カットを挟み、終盤で再び7〜9mmの印象カットを置く。この型は、短尺から中尺まで流用できます。
音声は、導入は環境音を多め、本編はナレーション優先、締めは環境音へ戻す構成が魚眼映像と相性が良いです。
このテンプレートで撮ると、魚眼の個性を活かしつつ、視聴者が情報を取りこぼしにくい動画になります。
まとめ
RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STMは、7mmの強烈な演出力と14mmの実用性を一本にまとめた、動画向けに非常に面白いレンズです。全周190°、明るい開放値、0.15m近接、ドロップイン対応、2D 180°VR対応という要素は、どれも動画制作で直接効きます。([Canon(Japan)][3])
使いこなしの鍵は、魚眼効果を前面に出すことより、何を見せる映像かを先に決めることです。7mmを演出、10〜14mmを説明に分け、シャッターとNDを管理し、移動速度を丁寧に整える。この運用で、派手さと見やすさを両立した動画を作れます。
一本目は完璧を狙わず、同じ場所で7mm・10mm・14mmを撮り比べるだけでも、すぐに自分の正解が見えてきます。