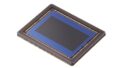冬の冷たい空気が張り詰める朝、武蔵丘陵森林公園に足を運びました。目的は、この季節ならではの美しい野鳥たちとの出会いです。霜が降りた地面を歩きながら、耳を澄ませば、鳥たちのさえずりが響き渡ります。カメラを片手に進むと、そこにはトラツグミやカワセミなどの特別な姿がありました。彼らが見せる瞬間の美しさは、一枚の写真に収めるだけでは伝えきれない感動そのものです。この日、私はそんな奇跡的な瞬間を求めて、ひたすらレンズを向け続けました。
野鳥を撮りに森林公園へ 2025/1/16 トラツグミやカワセミの特別な瞬間
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 640 |
武蔵丘陵森林公園では、野鳥たちが季節の移り変わりとともに特別な光景を見せてくれます。今回、トラツグミが地上で餌を探す姿や、カワセミが水辺に舞うシーンを目にしました。その一瞬一瞬が、まるで自然が贈る魔法のようでした。訪れるたびに新しい発見があり、カメラを持つ手にも力が入ります。公園を包む静けさの中で、野鳥たちの動きに耳を傾けながら撮影を楽しむ時間は、私にとって何ものにも代えがたい特別なひとときでした。
野鳥を撮りに森林公園へ
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 500 |
- 桜(花木園)でトラツグミを撮影
- 寺田沼でカワセミを観察
- ふれあい広場でルリビタキを撮影
桜(花木園)でトラツグミを撮影
森林公園に野鳥の撮影に行った。
南口から入り、桜(花木園)へ。どうも今シーズンはこの桜(花木園)は野鳥の数が少ないように感じる。そんな中突然足元から木の枝へ飛び立った鳥がいた。かえってそうしてくれたおかげで撮影しやすかった。見たことがあるようなないような。あとで調べるとトラツグミであった。おそらくそれほど珍しい鳥ではないだろうが、私にとっては初めての鳥で、初めて撮った鳥であった。
寺田沼でカワセミを観察
その後、寺田沼へ。再度コースを変えて桜(花木園)に戻り、再び寺田沼へ。
すると低空飛行をする物体が・・・。何年かぶりの寺田沼でのカワセミだった。やはり地元のカワセミは遠い。いや近所に比べるとそれなりに人通りがあるからまだマシであっただろうか。
寺田沼はまだ手前側が凍っている。つまりよくカワセミが現れる左岸の倒木のあたりは凍っていた。今までみたことのない右岸の木の枝にとまって獲物を探している。飛び込んだ。あまり綺麗ではないが、一応飛び込む様子も撮影することができた。やがて奥のブッシュの裏に隠れてしまい、いつの間にかいなくなった。
凍った水面をテケテケとキセキレイが歩いてきた。
梅林(花木園)に行くと、いつもの一番手前のところに福寿草が咲いていた。また少し奥に入ると少し多めに咲いていた。梅林(花木園)はいつもツグミ、ジョウビタキのメスなどがいるが、今年はジョウビタキのオス、モズくらいしか見ていない。この日も梅林(花木園)では野鳥を見ることはできなかった。
真ん中よりやや上、また上のトイレの近くにロウバイが咲いていた。森林公園のホームページに梅が開花したと書いてあったので3周ほどして探したが見つけることはできなかった。
ふれあい広場でルリビタキを撮影
いつものようにふれあい広場に向かう。以前2回ほど見たミヤマホオジロが目当てだが、いつもミヤマホオジロか?と感じる鳥はおそらくアオジだろう。
ここで地面にいる鳥を発見した。ファインダー越しに見るとメジロに見える。メジロが地面にいるというのも珍しいと思いながらシャッターを切ったのだが、正体はルリビタキのメスだった。これで毎年の目標のルリビタキのオス、メスを撮ることに成功した。やがてルリビタキが他の鳥に追い立てられている。ジョウビタキのメスだ。ルリビタキほどではないものの、やはりジョウビタキはオス、メスともに撮らないと落ち着かない。
さらにビンズイ。ビンズイもあまり頻繁に見る鳥ではない。
あとは、シジュウカラ、メジロ。うちにも来るがロケーションが違うので絵になる。
以前森林公園でシジュウカラを撮影していると、シジュウカラがいた方向から来た初老のカップルがいた。ありがちだが男性はまったく気を遣う様子もない。たいてい女性は気を遣ってくれたり、声をかけてくれたりするものだが、その女性は「シジュウカラでしょ」と軽くマウントを取るような言い方をした。私はシジュウカラを撮るときにそのエピソードを思い出すのだが、身近なシジュウカラであっても、シチュエーションや取り方によっては芸術作品になると考えている。
西田沼の脇を通り、山田城を一周、中を突き抜け南口近くの水場へ。そして南口から出た。
ふれあい広場から南口の間は運がよければルリビタキというところだが、なかなか野鳥が現れるスポットがない。そのうちセツブンソウなどが咲いたら、新たなルートが見つかるか?と考えている。
野鳥を撮りに森林公園へ
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 640 |
- トラツグミ
- カワセミ
- キセキレイ
- ジョウビタキ
- ルリビタキ
- ビンズイ
- シジュウカラ
- メジロ
トラツグミ
トラツグミ(Zoothera dauma)は、日本を含むアジア全域に分布する中型のツグミ科の鳥である。全長約29~31センチメートルで、ツグミ科の中でも比較的大型に分類される。体の上面は茶褐色で黒い斑点が広がり、胸部と腹部は白地に黒い波状の模様が特徴的である。この模様が虎の縞模様を連想させることから「トラツグミ」と名付けられている。地上性の鳥で、主に落ち葉の下に潜む昆虫やミミズ、果実を採食する。冬季には森林や雑木林の地面で観察されることが多いが、警戒心が非常に強く、気配を感じると素早く飛び去るため、近距離での観察は困難である。夜行性に近い性質を持ち、夜間や早朝に活動することが多い。また、「ヒトコエ鳥」としても知られ、その哀愁を帯びた鳴き声が夜間に響き渡る姿が幻想的である。繁殖期は春から初夏で、巣は地上に近い木の枝や低木の中に作られる。1度に3~4個の卵を産み、親鳥は献身的に雛を育てる。近年では、都市部周辺の緑地でも観察されるようになり、環境適応能力の高さが示されている。トラツグミは、文化的な側面でも注目され、古くからその鳴き声が文学や音楽に取り入れられてきた。これらの特徴から、トラツグミは観察者や研究者にとって非常に興味深い鳥と言える。
カワセミ
カワセミ(Alcedo atthis)は、ブッポウソウ目カワセミ科に属する美しい鳥で、全長は約16~18センチメートルである。日本国内では河川や池、湖沼などの水辺環境で広く観察される。その鮮やかな青色と光沢を持つ背中、オレンジ色の腹部が特徴で、「青い宝石」として知られる。カワセミの食性は魚類が主であり、小魚を捕食するためにホバリング(空中停止)からの急降下ダイブという独特の狩猟スタイルを持つ。水面へのダイナミックな突入は、多くのバードウォッチャーや写真愛好家を魅了している。繁殖期は春から夏にかけてで、崖や土手の垂直面にトンネル状の巣穴を掘り、その中で卵を育てる。オスは求愛行動として小魚をメスにプレゼントすることで知られ、この行動は繁殖の成功に重要な役割を果たしている。カワセミは縄張り意識が非常に強く、同種間で激しい争いが見られることもある。近年では都市部の公園や人工池でもその姿が観察されるようになり、環境適応能力の高さが注目されている。一方で、生息地の減少や水質汚染により個体数が減少している地域もあるため、保全活動の必要性が高まっている。カワセミの存在は、清浄な水環境を示す指標種としても重要であり、その生態や行動は環境学的にも注目されるべき対象である。
キセキレイ
キセキレイ(Motacilla cinerea)は、セキレイ科に属する小型の鳥で、全長約20センチメートルである。日本国内では渓流、湖沼、湿地などの水辺環境で広く見られる。特徴的な黄色い腹部と灰色の背中、そして長い尾羽を持つ。尾を頻繁に上下に振る独特の動作が名前の由来とされる。キセキレイの主な食性は昆虫であり、地面を歩き回りながらエサを探す姿がよく観察される。繁殖期は春から初夏で、岩の隙間や建物の構造物の中に巣を作る。巣作りには苔や植物繊維が利用され、親鳥は献身的に雛を育てる。鳴き声は澄んだ高音で、さえずりは非常に心地よく、他のセキレイ類と区別される。キセキレイは非常に清潔な水域を好むため、その存在は環境の健全さを示す指標とされることがある。一方で都市部や農地近くでも観察されることがあり、人間活動にある程度適応していることが示されている。しかし、水質汚染や生息地の減少が進む地域では個体数が減少しているため、保護が必要とされる場合もある。キセキレイは、日本だけでなくヨーロッパやアジアの広範囲で見られるが、地域ごとに異なる生態的特徴を示すため、研究者にとっても興味深い対象である。
ジョウビタキ
ジョウビタキ(Phoenicurus auroreus)は、ヒタキ科に属する小型の鳥で、全長は約14~15センチメートルである。冬鳥として日本各地に飛来し、公園や庭先、農村部などで広く観察される。オスとメスで体色が異なり、オスは鮮やかなオレンジ色の腹部と黒い頭部、白い翼斑が特徴的である。一方、メスは全体的に淡い茶色の体色を持ち、控えめな美しさを感じさせる。ジョウビタキの食性は主に昆虫で、地面や樹木の間を飛び回りながら捕食する。冬季には果実や種子も採取するため、野生植物の分布や環境保護に重要な役割を果たしている。
繁殖地は主にユーラシア大陸北部の森林地帯であり、日本国内では繁殖を行わない渡り鳥として知られている。繁殖期には、オスが縄張りを形成し、鮮やかな羽色とさえずりでメスを引き寄せる。縄張り意識が非常に強く、他の個体が侵入すると激しい追尾行動を示すことがある。ジョウビタキの鳴き声は、「ヒッヒッ」という警戒音や、美しいさえずりで構成される。冬の風物詩として広く親しまれており、初心者でも観察しやすい鳥の一つである。
また、ジョウビタキはその親しみやすい性格から、都市部でも頻繁に観察されるようになった。住宅地の庭に巣を作ることは少ないが、餌台や水場を設置することで観察機会を増やすことができる。環境の変化に適応する能力が高く、広範囲での分布が確認されている一方、森林伐採や農地の拡大による生息地の減少が懸念されている。そのため、自然環境の保全がジョウビタキの持続的な生息において重要な課題となっている。
ルリビタキ
ルリビタキ(Tarsiger cyanurus)は、ヒタキ科に属する小型の鳥で、全長は約13~15センチメートル。冬鳥として日本の里山や低山地帯に渡来するが、高山帯で繁殖する夏鳥としても知られている。オスは鮮やかな青色の羽毛を持ち、特に尾羽の美しい瑠璃色が名前の由来である。一方、メスや若鳥は全体的に淡い褐色の体に青い尾羽が特徴的である。ルリビタキの食性は主に昆虫やクモで、冬季には果実を食べることもある。枝から枝へと軽快に飛び回りながら採餌する姿が観察者を魅了する。
繁殖期は春から夏で、高山地帯の針葉樹林や落葉広葉樹林で巣作りを行う。巣は地上近くの茂みや樹木の根元に作られ、苔や植物の繊維を利用して精巧に作り上げられる。一度に産む卵の数は3~5個程度で、親鳥は協力して育雛を行う。冬季には平地や低山地帯に移動し、人里近くでその姿を見ることができるが、非常に臆病な性格のため、観察には静かな環境が必要である。
ルリビタキは、その美しい羽色と愛らしい仕草から「森の宝石」と称されることもある。日本国内では比較的安定した個体数を保っているが、森林伐採や都市化による生息地の減少が一部で懸念されている。特に高山帯の森林環境が重要であり、保護活動が求められている。また、ルリビタキは日本の文化や詩歌にも登場し、美の象徴として多くの人々に愛され続けている。彼らの生息環境を守ることは、自然環境全体の保全にもつながる重要な取り組みである。
ビンズイ
ビンズイ(Anthus hodgsoni)は、セキレイ科に属する小型の鳥で、全長は約15~16センチメートル。日本国内では主に冬季に平地や農地、草原などで観察されることが多いが、高山帯や亜高山帯では繁殖期にもその姿を見せる。スズメに似た体形を持つが、全体的に淡い褐色の体と黒い縦斑が特徴的で、飛翔時の波状飛行が目立つ。ビンズイの主な食性は昆虫や小さな種子であり、地面を歩きながらエサを探す姿がよく観察される。
繁殖期は春から初夏にかけてで、巣は地面に近い茂みや草むらに作られる。苔や細かい植物を材料にして作られた巣は、周囲と見事に同化しており、天敵から雛を守る工夫が凝らされている。1度に産む卵の数は4~6個程度で、親鳥は交代で抱卵と育雛を行う。ビンズイの鳴き声は、「チチチ」という軽快な音と美しいさえずりが特徴であり、特に繁殖期にはオスが積極的に歌声を響かせる。
ビンズイはその適応力の高さから、森林伐採や農地拡大といった環境変化にも柔軟に対応してきたが、一部地域では個体数の減少が報告されている。そのため、生息環境の保全や持続可能な農業との共存が重要である。観察者にとっては、その地味な外見に反して多様な生態を持つビンズイは、野鳥観察の興味を深める対象となっている。
シジュウカラ
シジュウカラ(Parus minor)は、スズメ目シジュウカラ科に属する小型の留鳥で、日本全国に広く分布している。全長は約14センチメートルで、黒い頭部と白い頬、黄色い腹部が特徴的である。体の中央には黒いラインが縦に入っており、これがオスとメスを識別するポイントとなる。オスはこのラインが太く、メスはやや細いのが一般的である。シジュウカラは森林、公園、庭先など多様な環境に適応し、特に人の手が加えられた環境でも繁栄しているため、都市部でも頻繁に見られる。
食性は雑食性であり、昆虫やクモを主に食べるが、植物の種子や果実も採取することがある。秋から冬にかけては、餌が乏しくなるため、人が設置した餌台を訪れることも多い。特にヒマワリの種が好物で、餌台での観察が容易である。シジュウカラは非常に社会性が高く、冬季にはエナガやコゲラなどの他の鳥種と混群を形成することがよくある。これにより、捕食者から身を守る効果があると考えられている。
シジュウカラの繁殖期は春から初夏にかけてで、巣は木の洞や巣箱などに作られる。草やコケ、羽毛を利用して柔らかい巣を作り、一度に6~12個程度の卵を産む。親鳥は交代で抱卵し、雛が孵化すると昆虫を頻繁に運び入れる姿が観察できる。雛は約2週間で巣立ち、親鳥からの給餌を受けながら独立する準備を整える。
シジュウカラは、その多彩な鳴き声でも知られている。「ツツピー」「ジュジュ」という鳴き声が一般的だが、警戒音や他個体とのコミュニケーションに使う特殊な鳴き声も持っている。研究では、シジュウカラの鳴き声には文法的な構造があることが示され、鳥類の認知能力の高さを示す一例となっている。こうした知見は、シジュウカラが環境の変化に敏感であり、その行動や分布が生態系の健康状態を示す指標になることを示唆している。
メジロ
メジロ(Zosterops japonicus)は、スズメ目メジロ科に属する小型の野鳥で、全長は約12センチメートル。日本全国で広く見られる留鳥であり、庭先や公園、山林など多様な環境に適応している。メジロの最大の特徴は、目の周囲にある白いアイリングで、これが「メジロ」という名前の由来となっている。また、全体的に緑がかった黄色い体色と細いくちばしが、美しい外見を際立たせている。
食性は雑食性で、主に花の蜜、果実、昆虫を食べる。春にはサクラやウメの花に集まり、蜜を吸う姿が観察される。特にウメの花との相性は抜群で、日本の春を象徴する風景の一部となっている。秋にはカキやナツメの実を好んで食べ、これが植物の種子分散に寄与していることが知られている。メジロのくちばしと舌は蜜を効率的に吸うために進化しており、他の鳥が利用できない花の蜜を摂取することができる。
繁殖期は春から初夏にかけてで、木の枝に巣を作る。巣はコケや植物の繊維を利用してカップ状に作られ、周囲の環境と見事に調和するように設計されている。一度に2~5個の卵を産み、雛は約2週間で巣立つ。メジロの親鳥は非常に献身的で、頻繁に餌を運び入れる姿が観察される。
メジロは社交性が高く、繁殖期以外は群れを形成して行動することが多い。そのため、庭に餌台を設置すると、一度に複数のメジロが訪れることも珍しくない。また、メジロは美しいさえずりで知られ、「チリチリ」という軽やかな鳴き声が特徴である。この鳴き声は、繁殖期にはオスが縄張りを主張したり、メスにアプローチするために使用される。
人間との共存が進む一方で、都市化や農薬の使用による生息環境の悪化が懸念されている。しかし、メジロの適応力の高さから、都市部や郊外でもその姿を見ることができる。日本の文化にも深く根付いており、俳句や詩歌にも登場することが多い。こうした背景から、メジロは単なる野鳥としてだけでなく、日本の自然と文化を象徴する存在として広く親しまれている。
撮影した花
 EOS R5 RF85mm F2 MACRO IS STM F5.6 1/250秒 ISO 160 |
- 福寿草
- ロウバイ
福寿草
福寿草(学名:Adonis amurensis)は、キンポウゲ科フクジュソウ属に属する多年草で、日本、中国、ロシアなど東アジアの寒冷地を中心に分布している。春を告げる花として知られ、雪解けとともに地上に鮮やかな黄色い花を咲かせる。名前の「福寿」は幸福と長寿を意味し、縁起の良い植物とされるため、正月の飾りや贈答品としても親しまれている。花の直径は約3〜5センチメートルで、花弁のように見える部分は萼片である。太陽の光に反応して開閉する特性があり、曇りや雨の日には花が閉じる。この動きは光温度応答と呼ばれる生理現象によるものである。根茎にはアドニトキシンという強い毒性を持つ成分が含まれており、これが誤食による中毒事故の原因となるため取り扱いには注意が必要である。福寿草は冷涼で湿り気のある環境を好み、野生では山間部の林縁や草地に自生している。園芸では水はけの良い土壌を選び、直射日光を避けて育てると開花が促進される。また、栽培品種には花色が異なる「紅寿」「白寿」などがあり、多様な園芸的価値を持つ。
ロウバイ
ロウバイ(蝋梅、学名:Chimonanthus praecox)は、ロウバイ科ロウバイ属に分類される落葉低木で、中国原産の植物である。冬季に他の花が咲き誇ることが少ない中、透明感のある黄色い花を咲かせ、その独特な芳香で人々を魅了する。花弁は蝋細工のような質感を持ち、この特性が名前の由来となっている。ロウバイは主に庭園や公園で観賞用として植栽されるが、切り花としても人気が高い。樹高は2〜3メートル程度まで成長し、枝は細長く垂れ下がることが多い。花は主に前年に伸びた枝に着生し、開花期は12月から2月にかけてである。果実は卵形で成熟すると褐色になり、内部に含まれる種子には有毒成分が含まれている。乾燥した土壌を好むが、湿気が多すぎない限りさまざまな環境に適応するため栽培が容易である。薬用植物としても古くから利用され、漢方では果実や根を解熱剤や鎮痛剤として使用することがある。剪定や施肥を適切に行うことで、樹形の維持と開花の促進が可能であり、冬の庭を彩る重要な植物としての価値を持つ。
撮影機材
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 320 |
- Canon EOS R5
- RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
- RF85mm F2 MACRO IS STM
Canon EOS R5
Canon EOS R5はキヤノンのフルサイズミラーレスカメラで、約4500万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載しており、細部まで鮮明に描写できる能力を持つ。この高解像度により風景や野鳥などの細かいディテールを余すことなく捉えることが可能である。高速連続撮影はメカシャッターで最大12コマ/秒、電子シャッターでは最大20コマ/秒に達し、動きの速い被写体に対しても優れた追尾性能を発揮する。8K動画撮影に対応しているため、プロフェッショナルの映像制作にも十分な性能を備えている。さらに、5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載し、低シャッタースピードでの撮影時にも高い安定性を実現している。操作性にも優れ、電子ビューファインダーの解像度は576万ドットで視認性が高く、タッチパネル式の液晶モニターも直感的な操作を可能にしている。デュアルカードスロットを備え、CFexpressとSDカードの両方に対応することで、データの書き込み速度と容量に柔軟性を持たせている。耐候性設計も施されており、雨天や過酷な環境でも安心して使用できる。これらの特長により、野鳥撮影のような要求の厳しいシチュエーションでも活躍する万能機種として評価が高い。

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMはキヤノンのRFマウント専用の超望遠ズームレンズであり、幅広い焦点距離をカバーすることで野鳥やスポーツ撮影に最適である。このレンズは100mmから500mmまでの焦点距離を持ち、遠距離から近距離まで柔軟に対応できるため、多様な撮影シーンで活用できる。光学設計にはスーパーUDレンズ1枚とUDレンズ6枚が採用されており、これにより色収差や歪みを最小限に抑え、高コントラストかつシャープな画像を提供する。内蔵された手ブレ補正機構は最大5段分の補正効果を発揮し、手持ち撮影時でもクリアな画像を得ることが可能である。また、リング型ナノUSMを採用することで、高速かつ静かなオートフォーカスを実現し、動きの速い被写体でも正確に追尾できる。レンズ筐体にはフッ素コーティングが施されており、ホコリや水滴が付着しにくい設計となっている。さらに耐候性が確保されており、厳しい環境下でも信頼して使用できる点がプロフェッショナルユーザーからも高い評価を得ている。ズーム操作はスムーズで、使用感の調整も可能なズームトルク調整リングを搭載しており、ユーザーの好みに合わせた操作ができる。特に飛翔する鳥の撮影や、遠く離れた被写体のディテールを捉える際にその真価を発揮するレンズである。

RF85mm F2 MACRO IS STM
RF85mm F2 MACRO IS STMはキヤノンのRFマウントに対応した中望遠単焦点レンズで、ポートレートやマクロ撮影に特化した特性を持つ。このレンズはF2の明るい開放絞りを採用しており、美しいボケ味を活かした撮影が可能である。0.5倍のマクロ撮影能力を持ち、最短撮影距離はわずか0.35メートルであるため、細かいディテールを鮮明に捉えることができる。特に小さな被写体を撮影する際には、その性能が顕著に発揮される。STM(ステッピングモーター)による滑らかで静かなフォーカス駆動が特徴であり、動画撮影にも適している。さらに手ブレ補正機構が内蔵されており、最大5段分の補正効果を提供することで、手持ち撮影時でも安定した画像を得ることが可能である。コンパクトで軽量な設計により、持ち運びが容易でありながら、堅牢性に優れた金属製のマウントを採用している点も安心感を与える。描写性能においても中心から周辺まで均一なシャープネスを実現し、ポートレート撮影では被写体の肌の質感を美しく再現することができる。さらに、マクロ撮影では細部のディテールを克明に描写し、昆虫や花の撮影においても満足のいく結果を得ることができる多用途なレンズである。

国営武蔵丘陵森林公園の紹介
 EOS R5 RF85mm F2 MACRO IS STM F4 1/1600秒 ISO 160 |
- アクセス情報
- 公園の歴史
- 施設と設備
- 草花と植生
アクセス情報
国営武蔵丘陵森林公園へのアクセスは、全国から航空機および新幹線を利用して訪れることができます。以下に、地域ごとに分けてアクセス方法を記載します。
航空機を利用したアクセス
- 北海道から: 新千歳空港から羽田空港へ(約1時間30分)。羽田空港から電車で東京駅へ移動し、在来線または新幹線で森林公園駅へ。
- 東北地方から: 仙台空港から羽田空港へ(約1時間)。同様に東京駅から森林公園駅へ移動。
- 中部地方から: 中部国際空港(セントレア)から羽田空港へ(約1時間)。羽田空港から電車で森林公園駅へ。
- 関西地方から: 関西国際空港または伊丹空港から羽田空港へ(約1時間30分)。その後、東京駅経由で森林公園駅へ。
- 中国・四国地方から: 広島空港または高松空港から羽田空港へ(約1時間30分)。東京駅を経由して森林公園駅へ。
- 九州地方から: 福岡空港から羽田空港へ(約1時間30分)。東京駅を経由して森林公園駅へ。
- 沖縄から: 那覇空港から羽田空港へ(約2時間30分)。羽田空港から東京駅、森林公園駅へのルート。
新幹線を利用したアクセス
- 北海道から: 北海道新幹線を利用して新函館北斗駅から東京駅へ(約4時間)。東京駅から在来線または新幹線を利用して森林公園駅へ。
- 東北地方から: 東北新幹線で仙台駅から東京駅へ(約1時間40分)。東京駅から森林公園駅へ。
- 北陸地方から: 北陸新幹線で金沢駅から大宮駅へ(約2時間30分)。大宮駅から森林公園駅へ在来線で移動。
- 関東地方から: 東京駅や大宮駅から在来線を利用して森林公園駅へ(約1時間)。
- 中部地方から: 東海道新幹線で名古屋駅から東京駅へ(約1時間40分)。東京駅から森林公園駅へ移動。
- 関西地方から: 東海道新幹線で新大阪駅から東京駅へ(約2時間30分)。東京駅から森林公園駅へ。
- 中国・四国地方から: 山陽新幹線で広島駅または岡山駅から東京駅へ移動(約4時間)。東京駅から森林公園駅へ。
- 九州地方から: 九州新幹線で博多駅から東京駅へ(約5時間)。東京駅から森林公園駅へ。
森林公園駅からは公園の各ゲート(南口、中央口、西口)へのシャトルバスが運行しており、訪問者の利便性を確保しています。
公園の歴史
国営武蔵丘陵森林公園は、1974年7月22日に日本初の国営公園として埼玉県比企郡滑川町に開園した。この公園の誕生の背景には、都市部での急速な人口増加や産業の発展に伴う自然環境の悪化があった。高度経済成長期の真っただ中で、日本政府は国民に自然と触れ合う場を提供し、都市部の喧騒から離れてリフレッシュできる空間を作ることを目的として、全国に国営公園を整備する方針を打ち出した。武蔵丘陵森林公園はその第1号として計画された。公園の設計段階では、既存の自然環境を最大限に活かしつつ、人工的な要素を加えて四季折々の自然美を楽しめる景観が意識された。敷地面積約304ヘクタールという広大な土地は、元々里山や雑木林として利用されていた場所であり、多様な生態系が存在していた。開園当初から、この生態系を保護することが公園管理の重要な使命とされており、現在もその方針は引き継がれている。また、開園時には多くのボランティアが植樹や環境整備に協力し、市民と行政が一体となって公園を育てる姿勢が確立された。1990年代以降、レクリエーション施設の拡充が進められ、特にサイクリングコースやアスレチックエリアが追加されることで、家族連れやアウトドア愛好者にとって魅力的なスポットとなった。また、近年では環境教育の場としての役割も重視されており、地元の学校や団体が利用する学習プログラムや自然観察会が定期的に開催されている。さらに、2010年代以降はバリアフリー設備の充実や外国人観光客の受け入れ体制の強化が進められ、多様なニーズに応えられる公園へと進化を遂げている。公園は今でも進化を続けており、年間を通じて訪れる観光客や地元住民にとって、自然とのふれあいを楽しむ貴重な空間を提供し続けている。その歴史は、単に自然を保護するだけでなく、社会や時代のニーズに応じた変化と成長の物語でもある。
施設と設備
国営武蔵丘陵森林公園には、多彩な施設が整備されており、訪問者の年齢や目的を問わず楽しむことができる。注目すべき施設の一つは「ぽんぽこマウンテン」である。これは大きなトランポリンのような地形で、子供たちが安全に飛び跳ねながら楽しめる設計となっている。広々としたドッグランも人気の施設であり、ペット連れの訪問者が愛犬とともに自由に遊べる空間が提供されている。さらに、園内には全長約17kmにわたるサイクリングコースが整備されており、初心者から上級者まで楽しむことができる。自転車を持参しなくても、レンタサイクルサービスを利用することが可能で、家族連れや観光客にとって利便性が高い。また、アスレチックエリアやピクニックエリアもあり、子供連れの家族にとっても魅力的な施設が揃っている。花木園では四季折々の花々が楽しめる。春には桜やチューリップ、夏にはヒマワリやアジサイ、秋にはコスモスや紅葉、冬には梅や福寿草が見どころとなる。特に秋の紅葉シーズンには多くの観光客が訪れる。また、園内には飲食施設も充実しており、地元の食材を使った料理を提供するレストランや軽食スタンドが点在している。観光の合間に地元の味覚を楽しむことができる。さらに、森林公園はバリアフリー対応が進んでおり、高齢者や障害のある方も安心して利用できる設備が整備されている。車いすで移動可能な舗装された歩道や、バリアフリートイレが複数箇所に設置されており、誰もが快適に過ごせるよう配慮されている。各種休憩所も整備されており、自然の中でリラックスできる空間が提供されている。最後に、環境教育にも力を入れている施設として、自然観察エリアや学習プログラムが挙げられる。ここでは訪問者が自然とのふれあいを通じて、環境保護の重要性を学ぶことができる。これらの施設と設備は、国営武蔵丘陵森林公園が訪問者に多様な体験を提供するために設けられており、その充実ぶりは他の公園にない魅力を持っている。
草花と植生
国営武蔵丘陵森林公園は、四季折々の草花や植生が楽しめる自然豊かな環境を提供している。特に、広大な花畑や花木園では、さまざまな種類の植物が見られ、訪問者を魅了している。春には、桜、チューリップ、スイセン、ネモフィラが咲き誇り、華やかな風景を楽しめる。また、夏にはアジサイやヒマワリが彩りを添え、清涼感をもたらす。秋には、紅葉が見どころとなり、公園全体が色とりどりの景観に包まれる。特に紅葉シーズンは公園のハイライトであり、訪問者は色づいたカエデやモミジを楽しみながら散策することができる。冬になると梅や福寿草が見頃を迎え、寒い季節でも花々の魅力を堪能することができる。福寿草は春の訪れを告げる花として人気があり、写真愛好家にも注目されている。また、公園内には日本固有の植物や、地域特有の植生も多く存在する。例えば、山野草エリアでは、キキョウやホトトギスなどの珍しい花々が観察できる。このエリアは自然観察や植物の学習に最適で、訪問者が自然の多様性を深く理解する機会を提供している。さらに、公園は自然環境を活用した庭園デザインにも力を入れており、テーマ別の花壇や植栽が楽しめる。バラ園では、数十種類のバラが育てられ、その美しい花と香りが訪問者を魅了する。ハーブ園も設置されており、ローズマリー、ラベンダー、タイムなどの香り豊かなハーブが一堂に会している。これらは、見て楽しむだけでなく、ハーブティーや料理用としての利用方法も学べる。また、花以外の植物にも注目が集まる。森林エリアでは、ブナやナラなどの落葉広葉樹、スギやヒノキなどの針葉樹が混在しており、豊かな森林の生態系を形成している。訪問者はこれらの植生を通じて、季節ごとの変化や日本の自然環境の多様性を体感できる。公園内では、植物に関するイベントやワークショップも頻繁に開催されており、専門家によるガイド付きツアーも行われている。これにより、訪問者は植物の特性や育成方法、自然保護について学ぶことができ、自然への理解を深める貴重な経験を得られる。
国営武蔵丘陵森林公園で観察できる野鳥
国営武蔵丘陵森林公園は、日本の中でも野鳥観察の名所として知られ、四季折々にさまざまな野鳥を観察することができる。その多様性は、森林、草原、水辺といった複数の生態系が公園内に共存していることに起因している。特に冬季には、ジョウビタキやルリビタキ、トラツグミといった冬鳥が見られる。これらの鳥たちは、繁殖地である北方地域から移動し、温暖な日本で越冬するため、森林公園に立ち寄る。さらに、年間を通じて観察可能な留鳥には、シジュウカラやメジロ、エナガ、モズなどがいる。これらの種は主に昆虫や果実を餌としており、公園内の自然豊かな環境が餌資源として最適であることがうかがえる。また、水辺ではカワセミやアオサギ、マガモなども確認される。カワセミは鮮やかな青色の羽を持つことで「水辺の宝石」とも称され、その狩猟行動を観察するのは鳥好きにとって一つの魅力である。春から夏にかけては、繁殖期を迎えた野鳥たちがさえずりを披露する姿が印象的である。例えば、キビタキやオオルリといった渡り鳥は、その美しい鳴き声と鮮やかな羽色で訪問者を魅了する。これらの鳥たちは森林内の高い木々に営巣し、昆虫を主な餌としている。一方、秋には実り豊かな環境が多くの鳥たちを引き寄せる。特にヒヨドリは、公園内の実のなる木に群がり、大きな鳴き声でその存在をアピールする。野鳥観察は、初心者から経験豊富なバードウォッチャーまで楽しむことができる。公園内には観察小屋や展望台が設置されており、鳥たちの自然な行動を間近で観察するための設備が整っている。野鳥の多様性は、公園が地域の生物多様性の保全に重要な役割を果たしていることを物語っており、訪問者に自然の美しさとその価値を再認識させる機会を提供している。
まとめ

国営武蔵丘陵森林公園は、豊かな自然環境と多様な生態系を持つ、野鳥観察や撮影に最適なスポットです。広大な敷地には森林、草地、水辺が調和し、多くの野鳥が生息しています。四季折々の鳥たちが訪れるため、訪問者は常に新しい発見と感動を味わうことができます。秋から冬にかけては、ルリビタキやジョウビタキ、カワセミなどが目を引き、多くの野鳥愛好者を魅了しています。この公園では、観察に適した静かなエリアや、野鳥の生態を理解するための情報掲示が整備されており、初心者から経験豊富な観察者まで誰もが楽しむことができます。また、野鳥観察を通じて、自然環境との共生やその重要性についても学ぶことができます。観察時には静かに行動し、自然を尊重する姿勢が求められます。野鳥との一期一会の瞬間を楽しむことができるこの公園は、訪れる人々に特別な時間を提供してくれます。
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 3200 |
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 500 |
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 1600 |
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 1250 |
 EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 1250 |